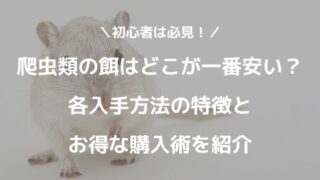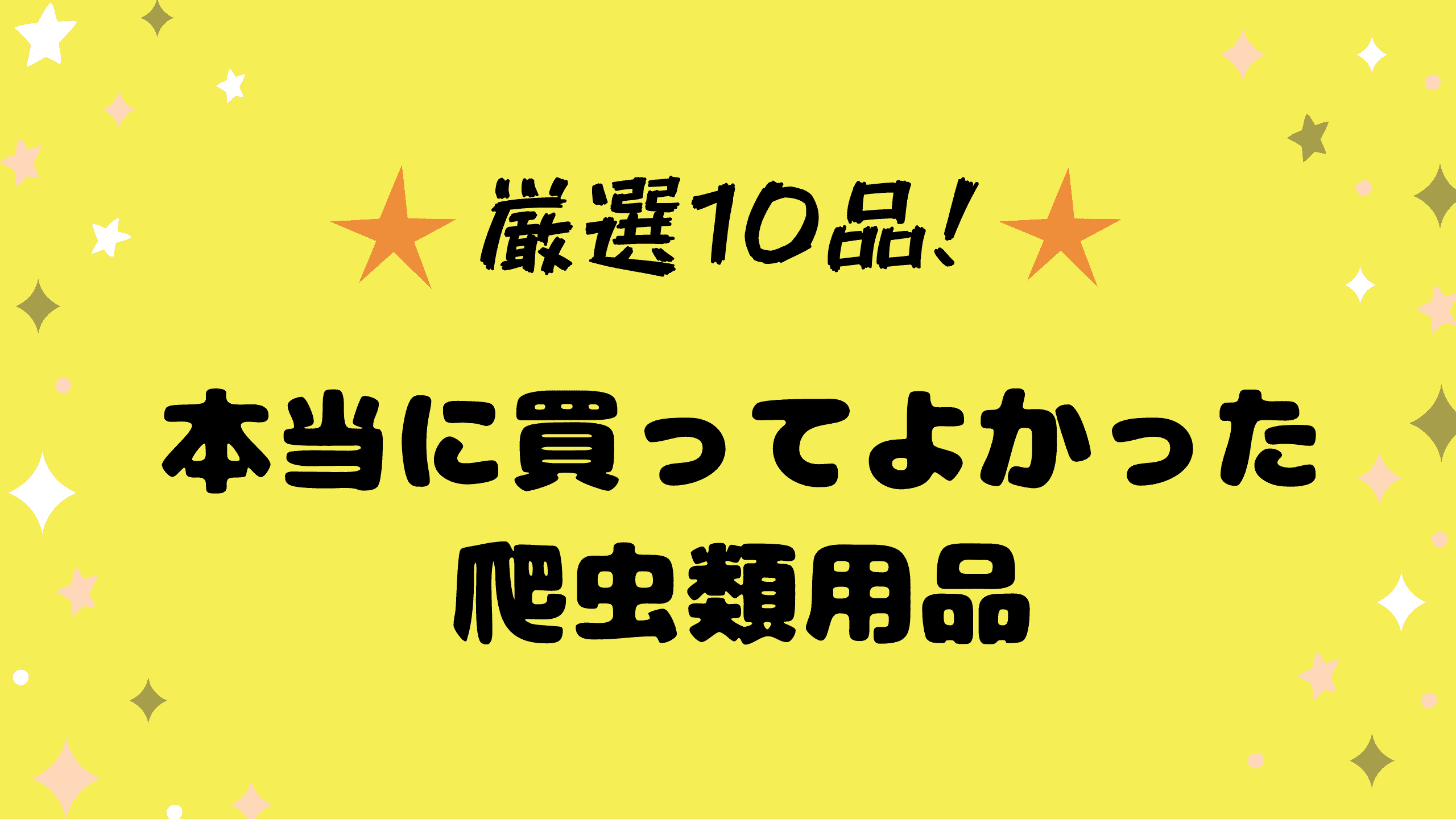ペットリザードは、爬虫類の中でも人気のジャンルの一つです。見た目の美しい種も多いため、飼育を検討している初心者の方は多いのではないでしょうか。
トカゲの飼育を考える中で、問題になるのが何を餌にできるのかという点。一口にトカゲと言ってもその食性は様々で、種によって食べる餌は異なります。
この記事では、ペットにできるトカゲ達の餌について解説していきます。
- トカゲの種類ごとの食性の違い
- 食性別に与えられる餌一覧
- 餌を与える際の注意点
このような内容を紹介します。
「トカゲが飼いたいけど餌は何を与えれば良いか分からない…」
こんな悩みをお持ちの方は参考にしてください。
目次
ペットトカゲの食性と与えられる餌は?

ペットリザードは「何を食べるのか」という点で、ざっくりと4つのグループに分けることができます。それぞれ与えることのできる餌や傾向が異なるので、飼育を始める前に知っておきましょう。
- 昆虫食タイプ
- 雑食タイプ
- 肉食タイプ
- 植物食タイプ
それぞれの特徴を見てみましょう。
昆虫食タイプ

昆虫を主食とするトカゲは、主に小型から中型種が多いです。主な餌は生きた昆虫と、昆虫が材料のフードです。
ニホントカゲやニホンカナヘビ、トカゲではありませんが地表性ヤモリのレオパードゲッコーなどが代表種です。
昆虫食の爬虫類に与えられる餌はいくつかバリエーションがあります。詳細は以下の通りです。
昆虫食爬虫類の代表的な餌(名称をクリックすると詳細ページに移動します)
| 名前 | 特徴 |
|---|---|
| コオロギ | 昆虫食爬虫類の代表的な餌 安価で入手しやすいがキープにはコツが必要 |
| ミルワーム | ゴミムシダマシの幼虫 入手しやすい反面脂肪が多く単食には向かない |
| デュビア | ゴキブリの仲間 体が大きく中型以上の種におすすめ 卵胎生なので繁殖が遅め |
| レッドローチ | ゴキブリの仲間 餌昆虫の中ではキープが楽な部類に入る 湿気がこもると異臭を発する場合あり |
| ハニーワーム | 蜂の巣を餌にする蛾の幼虫 嗜好性抜群だがハイカロリーで肥満になりやすい こちらも単食には不向き |
| シルクワーム | カイコの幼虫 嗜好性は高いがキープが手間で維持コストも高め |
| 人工フード | 昆虫食向けに作られた人工フード 「ペレット」「ゲル」「練り餌」 など多くのバリエーションが存在する。保存の手間がなく非常に便利だが個体によっては 全く口にしないこともある |
雑食タイプ

中型のトカゲに多い食性がこの雑食タイプです。ベビーからヤングまでは主に昆虫を中心に与え、成長後は野菜をメインに肉や人工フードをバランスよく与えます。
代表種はフトアゴヒゲトカゲやアオジタトカゲなど。飼育する上では嗜好性の高い昆虫ばかりを食べないよう、ある程度飼い主が成長に伴い餌をコントロールする必要があります。
肉食タイプ

大型のトカゲに多いのが肉食性のタイプです。幼い頃は昆虫をメインに、成長後はマウスやウズラなど、爬虫類用の冷凍肉を与えることが多くなります。
代表的な種だとサバンナモニターやサルバトールモニターなどが該当します。
一部例外はありますが、モニターと呼ばれるオオトカゲの仲間は肉食性のものが多いです。
植物食タイプ

ペットリザードの中には、植物のみを餌にするタイプのトカゲも存在します。一見活き餌を扱わずに済むので手軽に飼育できるようにも思えますが、人間との生活に慣らしが必要な種や、気性に難のある種も多いです。そのため初心者にはあまりおすすめできません。
ショップで取り扱っている種で最もメジャーなのはグリーンイグアナです。
植物食のトカゲの餌は、おおむね人間の食べる野菜と同じものです。しかし、中には食べ続けると体調を崩す可能性のある野菜や、与えられないものも存在します。自分で判断できない場合はショップに問い合わせてみると良いでしょう。
トカゲに餌を与える際の注意点

トカゲに餌を与える際は、いくつか注意点があります。哺乳類などのペットと比較すると留意する点が多いのであらかじめ確認しておきましょう。
具体的に、餌を与える際は以下の三点に注意してください。
- 冷凍餌は中まで解凍する
- 活き餌の逆襲に注意する
- 神経質な個体の餌やりにはコツが必要
それぞれ詳細を確認していきましょう。
冷凍餌は中まで解凍する
雑食や肉食のトカゲを飼育している場合、時にはマウスやウズラなどの冷凍肉を使用することがあると思います。この場合、しっかりと内臓まで温まっているかは注意が必要です。
というのも、冷たいままの解凍が不十分な餌は体調を崩す原因になるからです。吐き戻しや下痢、ひどい場合はお腹の中で排出できずに腐敗するケースもあります。
餌を与える前に、中まで解凍できているか実際に触って確かめてみてください。
冷凍餌を解凍する方法については以下でも紹介しています。

活き餌の逆襲には注意する
生きた昆虫を与える場合、活き餌の逆襲には注意してください。餌に体を齧られたり、捕食時に口内を傷つけられることがあります。特に、生きている昆虫を丸呑みして内臓を傷つけられてしまうと大怪我に繋がるかもしれません。
生体の負傷事故が最も多いのは、顎が大きく力の強いコオロギとジャイアントミルワームです。この二種類の餌は特に注意が必要です。
痛ましい事故を防ぐため、活き餌を使用する際はピンセットで頭を潰したり顎をカットしておくと安心です。
神経質な個体の餌やりはコツが必要
WC(野生下採取)個体や臆病な性格の個体の場合、いきなりピンセットで餌を持っていっても驚いて食べないことがあります。こういった場合、餌の与え方にも一工夫必要です。
餌を食べない時に試してみること
| ケース | 対処法 |
|---|---|
| ピンセットを怖がる | ケージ内に餌を撒く ※生体の負傷には注意 |
| 餌だと認識しない | 体液を出して臭いを強くしてみる 汁を舐めさせてみる |
| 人間が見ていると食べない | 活き餌が逃げられない容器に入れて置き給餌をする |
お腹は空いているはずなのに餌を食べない場合はお試しください。
餌やりにはサプリメントのダスティングが必須

爬虫類の餌は、多くの場合カルシウムやビタミンサプリメントのダスティングが必要です。飼育下で与えられる餌は種類が限られており、野生と比べると栄養が偏りやすいからです。
カルシウムやビタミンの不足から発生するくる病は、飼育下でしばしば見られる病気の一つです。カルシウムとビタミンをバランスよく取れているか、うまく吸収できているかは常に気にしてあげてください。
まとめ
一口にトカゲといっても、与えることのできる餌は様々です。食性に合わない餌を食べ続けることは体調の悪化に繋がるため、どんな餌を食べるのか確認することは非常に重要になります。飼いたい種類の特徴を把握し、適切な餌やりを行うようにしましょう。
- どんな餌を与えればいいのか
- 給餌頻度はどのくらいが適切なのか
飼育する上では、まずはこの二点を確認してみてください。
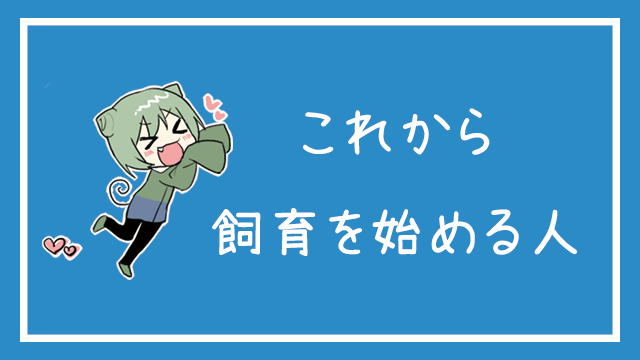
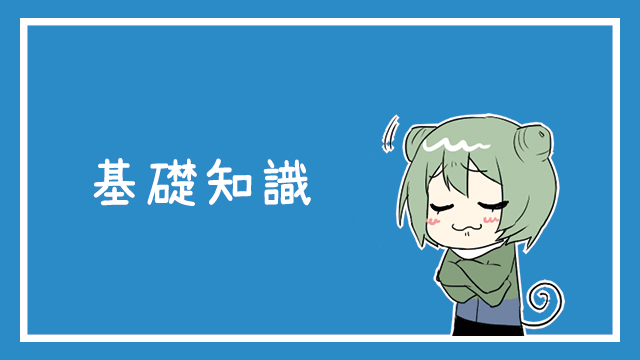




と購入予算を解説-320x180.jpg)