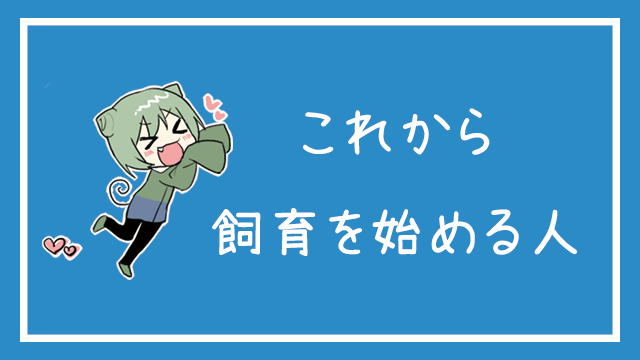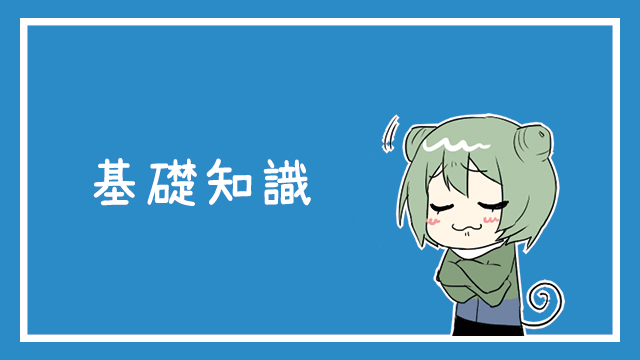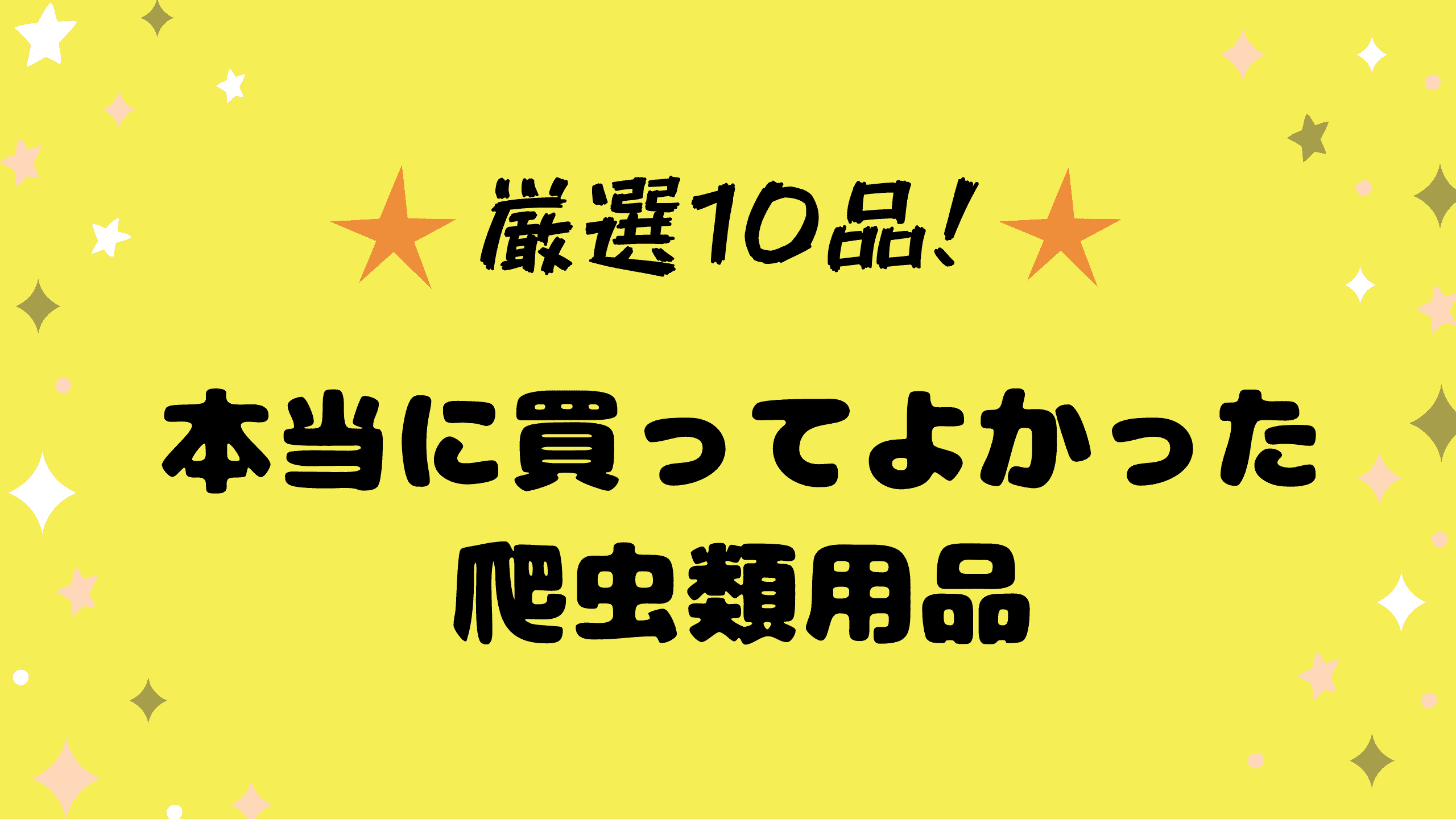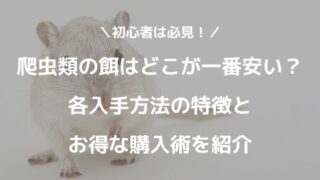珍しいペットを飼育してみたい方はコチラもご覧ください!

ヘビは怖いというイメージがあるかもしれませんが
実はペットとして飼育することができる爬虫類です。
ヘビはモルフ・品種の定着も進み、個体によってはとても美しい見た目をしています。
飼育自体も温度管理以外には難しいことはありません。
この記事では、初めてヘビを飼育する人でも飼いやすいヘビの種類とその飼育方法を紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
コーンスネーク

ヘビは見た目の怖さから凶暴だというイメージがありますが、
実はヘビの多くは性格がおとなしく、凶暴な性格をしているものはあまり多くありません。
その典型的なものがコーンスネークです。
性格はとても大人しくて、人を噛むというようなことは滅多にしないです。
ただし、口の前で指をぷらぷら揺らしているとエサと間違えて噛み付くこともあります。
大人になると、体長は1メートルから1メートル50センチくらいまで大きくなりますが、
飼育ケージは80センチ×50センチくらいで問題ありません。
ヘビは全般的に寒さに弱いので飼育するときにその点を配慮する必要があります。
このコーンスネークはヘビの中でも寒さにとても強い種類ですので、
パネルヒーターという保温器具があれば日本の冬の寒さにも十分耐えてくれます。
女性にも高い人気があるこのヘビは、見た目も美しくて初めて飼おうという人には本当におすすめです。
(2024/07/27 12:52:26時点 Amazon調べ-詳細)
カリフォルニアキングスネーク

コーンスネークと同様の、初めてヘビを飼育する人に人気のある種類があります。
それがカリフォルニアキングスネークです。
愛好家からはカリキンという略称で呼ばれています。
体長はコーンスネークとほぼ同じですから、飼育ゲージもほぼ同じくらいのものでいいでしょう。
ただし、とても細身の体型をしていますので、蓋がきちんとしまっていないとそこからするすると抜け出してしまうこともあります。
ヘビの中でも家から脱走されることの多いヘビでもありますので、その点はくれぐれも注意しましょう。
性格は大人しくて人を攻撃することはまずありませんが、
動きがコーンスネークよりも活発な分だけ飼い主はそれに驚いてしまうかもしれません。
環境によっては神経質になる個体もいますので、飼育したばかりの頃はハンドリングをするのは控えた方が良いでしょう。
神経質になっているかどうかを見極めるのは簡単です。
カリフォルニアキングスネークは尻尾を震わせて音を出していたら気持ちが高ぶっている証拠です。
このような状態のときは神経を逆なでしないようにしましょう。
カラーバリエーションがヘビの種類の中でも豊富でショップでいろいろと見てみるといいです。
哺乳類や鳥類から爬虫類まで何でも食べます。同種のヘビも食べてしまうことから、名前に「キング」が入っています。
(2024/07/27 12:52:27時点 Amazon調べ-詳細)
ボールパイソン

ボールパイソンもまた飼育しやすいヘビの1つです。
ボールのように丸まってしまうことからボールパイソンの名前が付きました。
コーンスネークに比べると少し神経質かもしれませんが、初心者の人でも問題なく飼うことができます。
体長は1メートルから2メートルまで大きくなります。
コーンスネークやカリフォルニアキングスネークより大きくて、太さもありますので、
飼育ゲージは100センチ×50センチくらいのものを用意するといいでしょう。
値段はコーンスネークやカリフォリニアキングスネークが1万円前後であるのに対して、
このボールパイソンは5000円から8000円くらいで買うことができます。
ただし、あまりにも安い個体は体が弱かったり、体調を崩しやすかったりしますので、購入するときには元気かどうかを観察することが大切です。
ボールパイソンの性格は臆病で人を攻撃することはなく、大人しいです。
臆病な性格が災いして環境が変わるとエサを食べなくなったりすることがありますので、
くれぐれもやさしく接する必要があります。
(2024/07/27 12:52:28時点 Amazon調べ-詳細)
セイブシシバナヘビ

セイブシシバナヘビも攻撃性がほとんどなくて飼いやすいヘビです。
体長が40センチから60センチ程度しかありませんが、
他のヘビにはない個性があるため、とても人気が高いです。
たとえば、ヘビには珍しく鼻が尖っていて顔立ちが格好良いところです。
体長は長くないのに全体的に太いです。
イモムシのような動きも特徴的で見ていて楽しめます。

セイブシシバナヘビの動画がこちらにまとまっていたので参考にしてみてください。

アオダイショウ

日本固有種で日本最大のヘビのアオダイショウです。
最大で2メートルになりますが、毒を持ちません。
日本では森林や家屋に住み着いていてネズミを捕食しています。
日本の環境に適応しているので飼育はさほど難しくありません。
といっても冬は加温しないと冬眠してしまうので気をつけましょう。
地域によって色が異なり、青、緑、オリーブ、黄、灰色とさまざま。
その中でも人気なのが白いアオダイショウ。通称白蛇です。
白蛇は神の使いとして祀られ、見た目も神々しいです。
アオダイショウを飼育する際は少し大きめのケージを用意してあげましょう。
半樹上棲なので立体運動が見られます。
アオダイショウの平均寿命は10年前後です。
飼育するに当たって用意するもの
飼育しやすいヘビの種類を紹介してきましたが、実際にはどのように飼育したらいいのでしょうか。
この4種類は基本的に同じように飼育することができます。まずは飼育ゲージを用意します。
これらのヘビは基本的にはとぐろを巻いてじっとしていることが多くて、とぐろを巻いている状態の3倍の床面積があれば十分です。
子供のうちは、レプタイルボックスで飼育ができます。大きくなったら大きいケージを使ってあげましょう。
30cmケージ
60cmケージ
また、ヘビを飼育するときに必須なものとして保温器具があります。
ヘビは寒さに弱いので気温が低くなってしまうと食欲を失って動かなくなります。
そのため、保温器具を設けて飼育ゲージの中を暖かくする必要があります。
室内に温度計を設置して温度管理してください。
ほかにも、大きめの水入れが必要です。
基本的には飲み水用ですが、ヘビは脱皮をするときに水の中に入りたがります。
そのため、ヘビの体がある程度入るくらいの大きさの水入れを準備しておきましょう。
エサは冷凍マウスが基本です。
1匹あたりにかかるエサ代は1ヶ月で500円くらいで済みますし、上記の4種類のヘビの好物でもあります。
ヘビの大きさに合わせて適切なサイズのピンクマウスを購入するといいでしょう。
目安としてはヘビの胴回りくらいの大きさのサイズです。
えさは毎日食べさせる必要はなく、週に1回から2回与えるだけでいいです。
十分成熟したらエサは週1回で十分です。
ボールバイソンのように神経質な種類の場合は、身を隠すためのシェルターを設置してあげましょう。
ショップに専用シェルターが売っていますし、ヘビが侵入できる穴を開けた木箱でもかまいません。
飼育する上での注意点
飼育用品を揃えてしまえば、あとはそのゲージの中に入れてエサを与えていればすくすくと育ってくれますが、
ヘビを飼育するときに注意することがあります。
それは1匹だけで飼育することです。
同じゲージの中に複数のヘビを入れていると、ケンカをしてしまうことがあります。
繁殖させるつもりがなければ、単独飼育が基本になります。
また、温度をこまめにチェックすることも大切です。
ヘビの種類と飼育方法のまとめ

ヘビは爬虫類の中でも特に飼育がしやすい種類です。
紹介したコーンスネークたちは、温度管理に注意を払う必要はありますが、エサを頻繁にあげる必要もなく簡単に飼育することができます。
ヘビに苦手意識がないなら、こうした大人しいヘビをペットとして飼育してみてはいかがでしょうか。