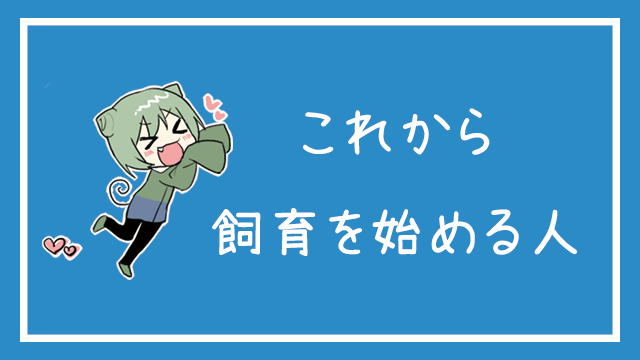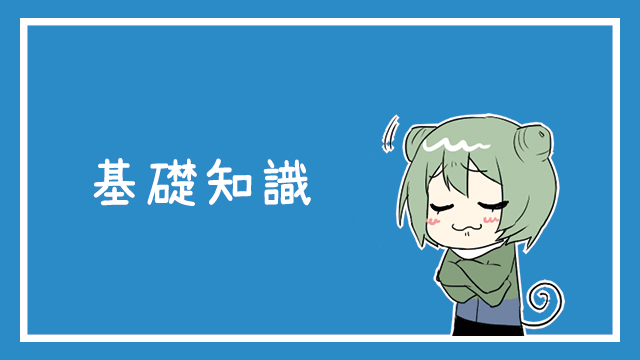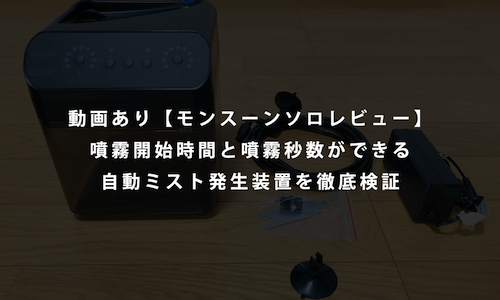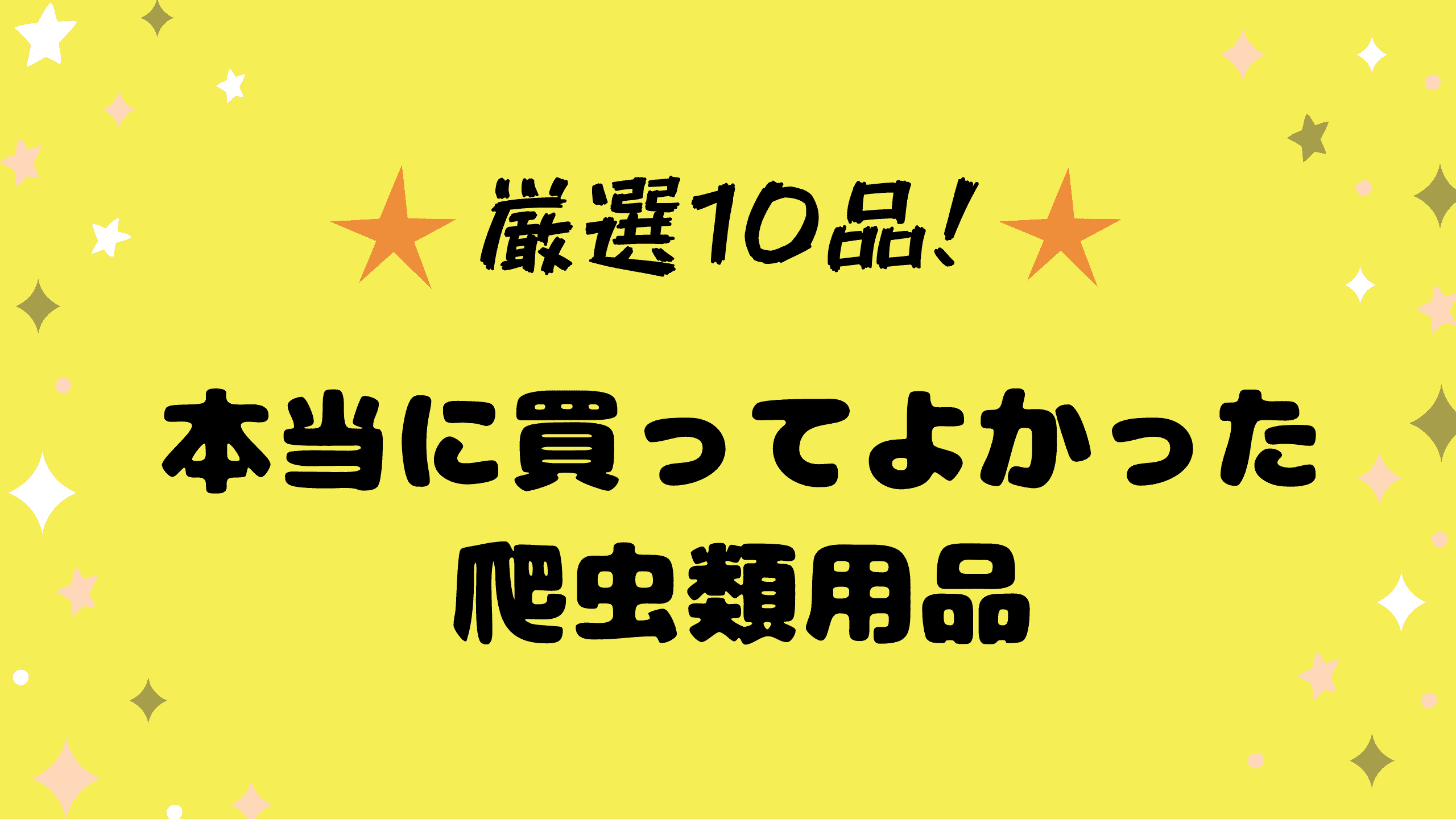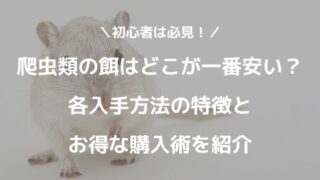夏から秋にかけて、野生のヘビたちの活動が活発になってくる頃です。
野性味の強い個体に惹かれ、採集に出かける人もいるかと思います。日本に住む蛇は、どんな種類が飼育可能なのでしょうか。
この記事では、日本に生息する蛇の中で比較的遭遇しやすい「アオダイショウ」と「シマヘビ」の飼育方法をご紹介します。
「外で蛇を捕まえたけど飼育方法がわからない!」
「ショップで売っている国産ヘビの飼い方を知りたい!」
そんな方に参考となる飼育方法をご紹介します!
目次
日本に分布する無毒ヘビで代表的な二種類
日本には、2019年現在、46種類のヘビが生息しています。(参考 日本産爬虫両生類標準和名リスト)
この中で、田んぼや森で遭遇しやすいのがアオダイショウとシマヘビです。
アオダイショウ
アオダイショウは、日本に生息するナミヘビ科の仲間で、「日本産のヘビでもっとも飼育のしやすいヘビ」と言われています。
国後・北海道・本州・四国・九州とその属島に分布する日本固有種。全長100〜160㌢が普通で、最大記録ははっきりしないが、2㍍はこえぬだろう。日本で最も飼育しやすい蛇の1種。
(参考 爬虫両生類飼育図鑑 p44)
体色は暗い緑色をしており、大きいもので2mほどの大きさになります。幼蛇の体色は成体とは全く異なり、茶色いヒョウ柄のような模様をしています。
アオダイショウは郊外の川辺や田んぼなどの水辺でよく見かける他、餌を求めて民家に入り込むこともあります。
餌は主に、小型の両生類や爬虫類、ネズミなどの小動物や鳥の卵などです。自分より体の小さい蛇も捕食します。
性格はおとなしく、人間を見かけても自分から襲いかかることはほとんどありません。
日本産の中では人気があり、爬虫類ショップでも販売されていることがあります。

シマヘビ
シマヘビもアオダイショウと同じナミヘビの仲間です。成体の全長は150cm前後とやや小柄です。
頭から尻尾にかけて、特徴的長い縞模様が4本見られます。幼蛇の頃は茶色〜赤みがかった体色で横縞があり、シマヘビも成体とは違った体色が見られます。
水辺でよく見かけるアオダイショウに対し、シマヘビは畑や草原、森の中などでその姿が確認できます。餌はアオダイショウと共通する部分が多く、両生類や爬虫類、小動物など幅広い獲物を捕食します。
性格はアオダイショウと比較するとやや気が強く神経質です。身の危険を感じると飛びかかってくることも考えられるため、捕獲の際は注意して下さい。

野生個体は餌を食べない可能性がある
野生個体を飼育するにあたり、一点頭に入れておいて欲しいことがあります。
それは、「野生下で暮らしていた生き物は、生き餌しか食べない可能性がある」ということです。
通常、ヘビを飼育する場合は餌として冷凍マウスを与えますが、野生個体は冷凍マウスに慣れておらず、餌としてみなさない場合があります。
その場合は活マウスや活ガエルを餌として与える必要性があり、飼育のハードルが一気に上がります。
採取個体が冷凍餌に餌付かず、生き餌を用意するのが難しい場合は、元の場所に返すことも検討しましょう。
アオダイショウ・シマヘビの飼育方法
アオダイショウとシマヘビの飼育方法は、同じナミヘビ科の仲間であるコーンスネークの飼い方に準じます。
アオダイショウは半樹上棲なので、ご紹介する飼育用品に加え、木の枝や倒木などを入れると良いでしょう。
必要な飼育用品
アオダイショウ・シマヘビの飼育に必要なものは以下の通りです。
- 餌
- ケージ
- 保温器具
- 床材
- シェルター(必要に応じて用意)
- 水入れ
それぞれどんなものが必要かご説明します。
餌
餌は、ヘビにとっての完全栄養食である冷凍マウスを使用します。冷凍マウスは、通販やペットショップなどで購入ができます。
冷凍マウスのサイズは小さいサイズのピンクマウスから大きいサイズのリタイアマウスまで多く用意されていますので、個体に合った大きさを選びます。ヘビの胴回りと同じくらいの太さか、少し小さめのサイズが良いでしょう。
ケージ
ヘビのケージは、爬虫類専用ケージである「グラステラリウム」をオススメします。
グラステラリウムがオススメである理由は
- 脱走の防止になる
- 通気性が良い
- メンテナンス性が高い
ためです。
ヘビは非常に力が強く、プラケースの蓋やスライド式の蓋はこじ開けて逃げ出すことができます。グラステラリウムは観音開きのタイプで、扉のロックができるため脱走の防止につながります。
ケージの広さは最低でも、ヘビがとぐろを巻いた状態の3倍の床面積のものを用意します。
アオダイショウには高さがあるケージを選ぶと、立体行動を見ることができます。
保温器具
アオダイショウやシマヘビの適温は25℃前後です。
室内の温度が30℃を超える場合や、20℃を下回る場合は室内の温度調節をしてください。
ケージの下に敷いて温めるパネルヒーターを使用する場合は、ビバリアの「マルチパネルヒーター」がオススメです。
マルチパネルヒーターは、温度の調節が可能なので安心して使用することができます。
パネルヒーターの低温やけどが心配な方は、暖突か保温球を使用しましょう。
温度を一定に保つサーモスタットを使用すると温度管理が楽になります。
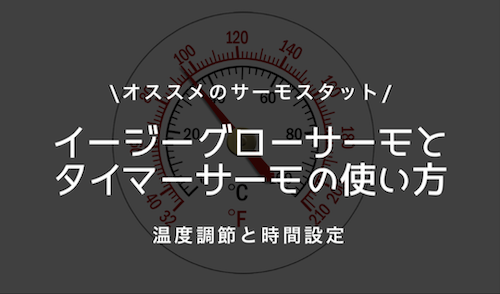
床材
ヘビに使用できる床材は
- 紙製
- 植物製
のものがありますが
ナミヘビ科のヘビの飼育には植物性のアスペンチップ(広葉樹チップ)がおすすめです。
なぜなら
- 潜って体が隠せるため安心する
- 糞尿・水零しでベチャベチャになりづらい
- 汚れた時に部分的な交換が可能
という利点があるためです。
アスペンチップの難点は、餌と一緒に誤食をする可能性があるという点です。少量であればフンとして排出されますが、誤食が気になる方はペットシーツを利用しましょう。
ペットシーツの利点は、掃除の度に交換するためケージ内が清潔に保たれることです。しかし、部分的な交換ができないため若干の手間がかかります。また、ヘビがシーツの下に潜り込んでしまうこともあります。
シェルター
ヘビの飼育には、シェルターの使用は必須ではありません。しかし、野生個体の場合、人間の存在にストレスを感じて体調を崩してしまう場合があります。
特にシマヘビはアオダイショウよりも臆病で神経質な性格をしていますので、姿を隠せるスペースを用意しておくことをお勧めします。
シェルターはヘビの全身が隠れる物であれば何でも大丈夫です。専用のシェルターも販売されていますが、大きめの植木鉢などでも代用できます。
水入れ
ヘビは水に体をつける習性がありますので、全身が浸かれるサイズの水入れを用意します。水入れは100均のタッパーなども利用できます。
水入れの水は、蛇の飲み水にもなっているので毎日交換するのが望ましいです。
日々のお世話
アオダイショウ・シマヘビの日々のお世話は大きく分けて以下の三種類です。
- 餌やり・水の交換
- 糞の掃除
- 温度管理
それぞれの項目についてご紹介します。
餌やり
給餌は、成体であれば週に1~2回、幼体の場合は週に2〜3回の頻度で行います。
冷凍マウスは湯煎で解凍を行います。50~70℃のお湯で解凍し、内臓まで解凍できれば与えて大丈夫です。マウスのお腹を触り、ぷよぷよとした感触になれば解凍されていると判断します。
掃除
糞をしたら早めに取り除くようにします。アスペンチップを利用する場合、糞の水分を吸い取っていますので、周りのチップごと回収して捨てるようにしてください。
まとめ
以上、シマヘビとアオダイショウの飼育方法をご紹介しました。
野生で生きていた個体は人間に対する警戒心が強く、ストレスによって体調を崩してしまうなどのトラブルも起こりやすいです。
拒食が続くようであれば早めに活餌の使用か、元いた場所に逃がすことも考えましょう。
屋外採取のヘビが餌を食べない・様子がおかしいといった問題がある場合、今回ご紹介した内容を参考に環境を見直してみて下さい。
ライター:いちはらまきを
Twitter:@IchiharaMakiwo